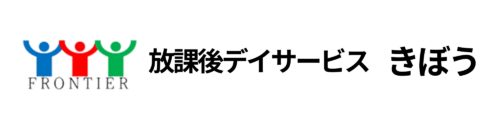絵カード交換式コミュニケーション(PECS)とは?
「言葉で伝えるのが苦手」「思っていることをうまく表現できない」
そんなお子さんにとって、コミュニケーションは大きなハードルになることがあります。
例えば、「ジュースが飲みたい」と思っても、言葉でうまく伝えられなければ、相手に理解してもらえません。こうした状況が続くと、「伝わらない」「話しても無駄」と感じてしまい、次第にコミュニケーション自体を避けるようになってしまうこともあります。
PECS(絵カード交換式コミュニケーション)は、こうしたお子さんの「伝えたい!」をサポートするための方法です。絵や写真を使って自分の気持ちや希望を伝えることで、言葉がなくても意思疎通ができるようになり、コミュニケーションへの意欲が生まれます。
どうやってコミュニケーションを助けるの?

PECSの基本は、「伝えたいものの絵カードを相手に渡す」というシンプルな仕組みです。
例えば、お子さんが「おやつを食べたい」と思ったとき、言葉で伝えなくても「おやつ」の絵カードを指さしたり、先生に渡したりすることで意思を伝えられます。最初は「欲しいものを伝える」ことから始め、慣れてくると「何が好きか」「どんな気持ちか」など、より多くの情報をやり取りできるようになります。
例えば、お子さんが「おやつを食べたい」と思ったとき、言葉で伝えなくても「おやつ」の絵カードを指さしたり、先生に渡したりすることで意思を伝えられます。最初は「欲しいものを伝える」ことから始め、慣れてくると「何が好きか」「どんな気持ちか」など、より多くの情報をやり取りできるようになります。
この方法の良いところは、「言葉を使わなくても伝わる」という安心感を持てることです。言葉に頼らずとも「伝わる体験」が積み重なることで、少しずつ自分から意思表示する力が育ちます。
PECSの6つのフェーズ
フェーズ1:コミュニケーションの方法を学ぶ
目標:お子さんが欲しいアイテムや活動に関する1枚の絵カードを、コミュニケーションパートナーに自発的に渡すことを学びます。
内容:お子さんは、欲しいものがあるときに、その絵カードを取り、相手に手渡すことで要求を伝えます。この段階では、絵カードの意味理解や選択は必要なく、行動としてのコミュニケーション方法を習得します。
フェーズ2:距離と持続性
目標:お子さんが、さまざまな場所や人に対して、絵カードを使ったコミュニケーションを自発的かつ持続的に行うことを目指します。
内容:お子さんは、コミュニケーションパートナーが離れた場所にいても、自ら移動して絵カードを渡しに行きます。これにより、コミュニケーションの一般化と持続性を高めます。
フェーズ3:絵カードの弁別
目標:お子さんが複数の絵カードの中から、欲しいものを正しく選択できるようになることを目指します。
内容:最初は好みのものとそうでないものの2枚のカードから選ぶ練習を行い、徐々に選択肢を増やしていきます。これにより、絵カードの弁別能力を高めます。
フェーズ4:文の構築
目標:お子さんが「○○がほしいです」といった簡単な文を構築し、要求を伝えられるようになることを目指します。
内容:「ほしい」という文カードと、対象の絵カードを組み合わせて文を作り、コミュニケーションパートナーに渡します。これにより、より具体的な要求表現が可能になります。
フェーズ5:質問への応答
目標:お子さんが「何がほしいですか?」といった質問に対して、適切に応答できるようになることを目指します。
内容:コミュニケーションパートナーからの質問に対し、適切な絵カードを選んで文を作り、応答します。これにより、双方向のコミュニケーション能力が向上します。
フェーズ6:コメントの表現
目標:お子さんが自発的に環境や出来事についてコメントできるようになることを目指します。
内容:「見て」「聞いて」などの文カードを使い、自分の感じたことや気づいたことを伝える練習を行います。これにより、コミュニケーションの幅が広がります。
PECSと自閉症やABAとの相性
PECSは、特に自閉症スペクトラム障害(ASD)のあるお子さんにとって有効な支援方法とされています。
言葉でのコミュニケーションが難しいお子さんでも、視覚的な情報を使うことで、スムーズに意思を伝えることができます。PECSを活用することで自閉症のお子さんのコミュニケーション能力が向上し、問題行動の減少や社会的相互作用の増加が見られると報告されています。
また、PECSは応用行動分析(ABA)の手法と密接に関わっています。ABAは、望ましい行動を強化し、望ましくない行動を減少させるための科学的手法です。
PECSはABAの原則に基づいて設計されており、適切なタイミングで強化子(ごほうび)を与えることで、子どもが積極的にコミュニケーションを取るように促します。
例えば、PECSを使い始めたばかりのお子さんが「ジュース」のカードを渡せた場合、すぐにジュースを渡すことで「カードを使えばほしいものがもらえる」ということを学びます。この成功体験を積み重ねることで、徐々に自発的なコミュニケーションが増えていきます。
きぼうでの取り組み
きぼうでは、お子さん一人ひとりの状況に合わせて、必要であればPECSの各フェーズを段階的に導入しています。最初は簡単な要求から始め、徐々に複雑なコミュニケーションへと進めていきます。また、PECSとABAの手法を組み合わせることで、効果的な支援を提供しています。

5領域について
お子様の身体・社会性・認知・感情・コミュニケーション能力をバランスよく育む取り組み。

TEACCHプログラムに基づいた支援
構造・可視化された学びの環境で、お子様の自立を促進するプログラム。

ABAを活用した支援
行動の前(きっかけ)と後(結果)を分析して適切な行動に変えるためのアプローチをおこなう手法です。

きぼう独自の課題学習
お子様の発達段階に応じた個別の支援内容を詳しく説明します。