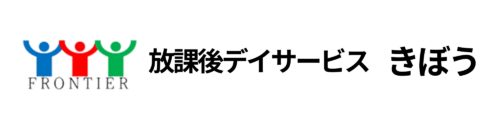きぼうの療育プログラムの基本理念
多様な友達や職員との日常の生活を通して、社会との関わりの大切さや楽しさを感じ、一人ひとりの個性が輝ける、そんな心和やからぐ放課後の居場所づくりに努めています。


きぼうの支援方針
こども達が健やかに、自信を持って
社会の中でたくましく生きていけるように。
「きぼう」は、お子さまが未来への一歩を踏み出す場所です。
きぼうでは、お子様一人ひとりの特性やペースを理解し、無理に集団行動を求めるのではなく、安心して挑戦できる環境を整えています。
独自に構成した課題学習や視覚的支援、ABAを活用し、生活スキルやコミュニケーション力を楽しみながら育成。変化への柔軟な対応力を養い、将来の自立につながる力を育みます。
また、成長は日々の積み重ね。ご家族と連携し、家庭でも活かせる支援を提供します。支援の目的は、今だけの満足ではなく、将来の笑顔です。お子様が自分の力で道を切り開き、社会の中でいきいきと自分らしく生きていけるよう、私たちは全力でサポートします!
お子さま本人への支援
健康・生活
お子様の清潔維持のために適度な手洗いを促し、登所・退所時の体温測定による定期的な心身状態の把握、適切なトイレ排泄の支援、ストレッチなどの軽い運動の実施、そして部屋ごとの役割を明確にする物理的構造化により、お子様の成長をサポートいたします。
- 適度に手洗いをしてもらうことで清潔の維持を支援
- 定期的な心身状態の把握(登所、退所時に体温測定を行ないます)を行なう
- 適切にトイレで排泄できるよう支援
- ストレッチなどの軽い運動を行なう
- 部屋ごとの役割を明確にし、この場所では何をするかを明確に提示(物理的構造化)
運動・感覚
姿勢保持の練習や指先を使う遊び、気温に合わせた衣類調整、食事のサポート、そしてみんなで楽しめる運動を通して、お子様の成長を楽しく支援します。
- バランスボールを使って姿勢保持の練習を行う
- ストレッチなどの軽い運動を行なう
- アイロンビーズや折り紙など指先を使う遊びを行う
- 気温や状況に合わせた衣類の着脱の支援を提供
- 食べ物摂取時に、必要に応じてクッションや補助用具等を使用して姿勢保持を行なったり、必要な物を要求するなど意思の伝達が出来るように支援
- 縄跳び、大縄飛び等、他の人と行なう運動の機会を支援
認知・行動
場所に応じた行動理解、指先を使った遊び、気候に合わせた調整力、数字や時間、日付の理解といった日常生活に必要なスキル習得を支援します。
- 部屋ごとの役割を明確にし、この場所では何をするかを明確に提示(物理的構造化)
- アイロンビーズや折り紙など指先を使う遊びを行う
- 気温や状況に合わせた衣類の着脱の支援を提供
- 数字や数の概念の理解を支援し、時計をみて行動に移せるようになったり、カレンダーなどをみて今日が何日かが解る様になるなど、日常生活に必要なスキル習得が出来るように支援
言語・コミュニケーション
書字や食事のサポートから、数字や時間の理解といった生活スキル、認知力育成、ABAに基づいた支援、視覚的な価値提供、集団ゲームを通じた社会性育成まで、お子様の様々な成長を丁寧にサポートします。
- 書字、運筆の練習を支援
- 食べ物摂取時に、必要に応じてクッションや補助用具等を使用して姿勢保持を行なったり、必要な物を要求するなど意思の伝達が出来るように支援
- 数字や数の概念の理解を支援し、時計をみて行動に移せるようになったり、カレンダーなどをみて今日が何日かが解る様になるなど、日常生活に必要なスキル習得が出来るように支援
- ピン差しやマッチング、分類など約200種類ある課題の中から本人の出来る、あるいは少し頑張れば出来る課題などを選んで行なっていくことにより、自尊心が育まれ、また形や色、空間の認知力が育成できるように支援
- 応用行動分析(ABA)の技法を使うことにより、感覚、認知、行動の偏り等に対して支援
- 何をして欲しいのかを絵や文字で示し、誤解無く伝わるように支援(視覚的構造化)
- 好きな遊びをしていても、切り替えて訓練に来てもらえるように支援
- 調理訓練を工程ごとに写真などを使ったレシピを作成し、これを基に準備から片付けまで児童主体で行なう支援
- 見学などの際は、行動予定を整理したパンフレットを作成し、混乱なく落ち着いて見学できるよう支援
- 小集団でのゲームを行ない、社会的行動形成の支援を提供
人間関係・社会性
日常生活に必要なマナーや社会のルールをSSTやソーシャルストーリーで学び、人との関わりを育みます。また、200種類以上の課題や個別化された様々な支援、楽しい駄菓子選びなどを通して、お子様の自尊心や認知力、意欲を高め、調理訓練や計画的な外出を通して自立を支援します。
- 社会的技能訓練(SST)の技法を用いて、日常必要枝をされる動作やマナーなどを練習、習得できるよう支援
- 社会の中での暗黙のルールや振る舞いなどを簡単な文章で示し、ソーシャルスキルの向上を支援(ソーシャルストーリー)
- 訓練の後に好きな駄菓子を選んで買う支援を提供
- イベントに参加してもらい、人との良好な関りやルールを理解して周囲との安定した関係を形成できるように支援
- 縄跳び、大縄飛び等、他の人と行なう運動の機会を支援
- ピン差しやマッチング、分類など約200種類ある課題の中から本人の出来る、あるいは少し頑張れば出来る課題などを選んで行なっていくことにより、自尊心が育まれ、また形や色、空間の認知力が育成できるように支援
- 応用行動分析(ABA)の技法を使うことにより、感覚、認知、行動の偏り等に対して支援
- 何をして欲しいのかを絵や文字で示し、誤解無く伝わるように支援(視覚的構造化)
- 好きな遊びをしていても、切り替えて訓練に来てもらえるように支援
- 調理訓練を工程ごとに写真などを使ったレシピを作成し、これを基に準備から片付けまで児童主体で行なう支援
- 見学などの際は、行動予定を整理したパンフレットを作成し、混乱なく落ち着いて見学できるよう支援
- 小集団でのゲームを行ない、社会的行動形成の支援を提供
ご家族に対して
保護者の皆様へ、困り事や将来のことなど何でもご相談いただければ、適切な支援とアドバイスを行ない、ご希望の方には支援計画の内容や方法を面談時にご説明いたします。
5領域の支援プログラムについて、詳細をPDFでご確認いただけます。
放課後デイサービス きぼうの支援内容にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。
お子様の成長を願う皆様へ、まずは放課後デイサービス きぼうの見学をおすすめいたします。温かい雰囲気の中で、お子様たちが安心して活動している様子をご覧ください。また、体験では、実際にどのような支援を受けられるのかをご体験いただけます。
見学と体験を通して、お子様の笑顔と成長をしっかりとサポートできるか、ご納得いただけるまでご確認いただければ幸いです。

TEACCHプログラムに基づいた支援
構造・可視化された学びの環境で、お子様の自立を促進するプログラム。

ABAを活用した支援
行動の前(きっかけ)と後(結果)を分析して適切な行動に変えるためのアプローチをおこなう手法です。

きぼう独自の課題学習
お子様の発達段階に応じた個別の支援内容を詳しく説明します。

絵カード交換式コミュニケーション
PECS(絵カード交換式コミュニケーションシステム)という絵カードを示して、コミュニケーションを行うシステムをコミュニケーションに難のあるこどもに教えていくこともできます。