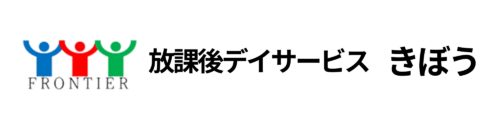きぼうオリジナルの課題学習とは?
お子さん一人ひとりに合った「できること」を見つけ、楽しみながらスキルを育てていく。それが、きぼうの課題学習です。
単に勉強をするだけではなく、「自分からやってみよう!」と思える工夫を取り入れ、学びの楽しさを感じてもらうことを大切にしています。
きぼうの課題学習の特徴
きぼうでは、課題学習を通じて「スキルを高める」「自尊心を育てる」「行動の切り替えをスムーズにする」ことを目的としています。
まず、お子さんが自然に学習に取り組める環境を整えることが重要です。
最初は一目見てすぐにできる簡単な課題から始め、「できた!」という成功体験を積み重ねることで、次のチャレンジにつなげていきます。慣れてきたら、少しずつ難易度を上げていき、考える力や集中力を養います。
また、遊戯室などで自由に遊んでいる最中でも、課題の順番が来たらスムーズに切り替えられるように支援しています。最初は「えー、やりたくない…」というお子さんでも、繰り返し経験を積むことで、「次は自分の番だ!」とスムーズに移行できるようになっていきます。こうした経験を通して、「やるべきことに取り組む力」や「行動の切り替え」を身につけていきます。
自尊感情を育む支援
なぜ「自尊心の向上」が大切なのか?
発達障害のある子どもは、学校や日常生活の中で「周囲と比較されること」が多く、劣等感を抱きやすい傾向があります。
国立特別支援教育総合研究所の研究でも、ADHDやLD、自閉症スペクトラムのある子どもたちは、「自分だけできない」と感じたり、失敗経験が積み重なることで自己評価が下がりやすいことが指摘されています。(参考とした調査資料はこちらをクリック)
だからこそ、きぼうでは「成功体験を積み重ねる支援」を大切にしています。
お子さんが「自分にはできることがある」「頑張ればできるんだ」と思えるような環境を整え、一人ひとりのペースに合わせた支援を行っています。
自尊心を育てる3つの工夫
「できた!」を積み重ねる
課題学習では、はじめから難しいことに挑戦するのではなく、最初は簡単なものから取り組みます。「これならできる!」という感覚を持つことで、自信をもって次のステップへ進めるようになります。
たとえば、計算問題が苦手なお子さんの場合、はじめは数字を並べるだけの課題から始め、次に簡単な足し算へと段階的に進めます。こうすることで、「自分はやればできるんだ」と実感でき、学ぶ意欲につながります。
失敗ではなく「努力」に目を向ける
発達障害のあるお子さんは、周囲と比べて「できないこと」に目が行きがちですが、大切なのは「挑戦しようとした気持ち」です。
当施設では、「結果」ではなく「取り組む姿勢」を大切にし、努力そのものを評価します。たとえば、「最後までやり遂げたね!」「時間をかければしっかりできるね!」といった声かけを行い、お子さんが「自分の頑張りを認めてもらえた」と感じられるようにしています。
自己理解を深める
「自分はどんなことが得意なのか」「どのような工夫をすればできるようになるのか」を、一緒に考える機会を大切にしています。例えば、「体育は得意だけど、勉強は少し苦手。でも時間をかければできる!」と気づくことで、焦らずに取り組めるようになります。「自分の強み」を知ることは、自尊心を高める第一歩です。
きぼうでの取り組みについて
実際の課題学習では、こうした支援を日常的に取り入れています。
はじめは「駄菓子をもらえるからやる!」という気持ちで取り組むお子さんも多いですが、それが悪いことではありません。最初は動機が何であれ、「課題に向き合い、やり遂げる経験を積むこと」が大切です。「頑張ったらご褒美がもらえる」 というシンプルな仕組みが、お子さんたちの「やってみよう!」という気持ちを引き出します。
しかし、続けていくうちに、変化が生まれます。最初は駄菓子のためにやっていたお子さんが、「もっと難しい課題に挑戦したい!」と自分から言い出すようになったり、駄菓子がもらえなくても「できたことがうれしい!」と感じるようになったりするのです。
この「楽しいからやる」「できるからやりたい」という感覚が、学習への前向きな気持ちを育む大きな要素 になっていきます。
おやつをきっかけに始めたことが、「できることが増えていく楽しさ」へと変わっていく。この経験こそが、お子さんの成長につながっていきます。

5領域について
お子様の身体・社会性・認知・感情・コミュニケーション能力をバランスよく育む取り組み。

TEACCHプログラムに基づいた支援
構造・可視化された学びの環境で、お子様の自立を促進するプログラム。

ABAを活用した支援
行動の前(きっかけ)と後(結果)を分析して適切な行動に変えるためのアプローチをおこなう手法です。

絵カード交換式コミュニケーション
PECS(絵カード交換式コミュニケーションシステム)という絵カードを示して、コミュニケーションを行うシステムをコミュニケーションに難のあるこどもに教えていくこともできます。